本記事は「現代医学の穴~東洋医学は補完できるのか?」シリーズの第2回です。
第1回ではEBM(根拠に基づく医療)の限界を整理しました。
現代医学の穴~東洋医学は本当に補完できるのか?②
画像診断は万能なのか?
現代医学において、レントゲン・エコー・CT・MRIといった画像診断は、診断と治療方針を決めるうえで欠かせない存在です。
体の内部を可視化することで、病変の有無や程度を客観的に確認でき、医療の精度を大きく高めてきました。
第1回で取り上げたEBM(根拠に基づく医療)においても、画像診断は「根拠」を支える重要な柱の一つです。
しかし、ここにもまた「強み」と同時に「限界」が存在します。
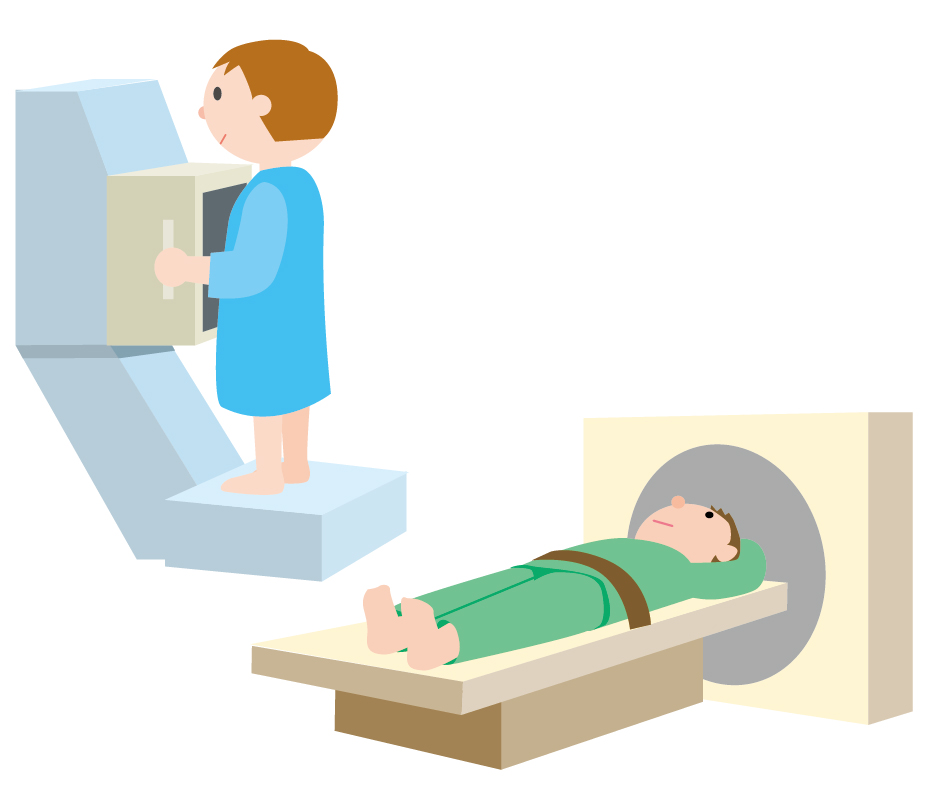
「よく見える」ことの功罪
画像診断の最大の利点は、
体の中が“見えてしまう”ことです。
これは診断において大きな武器になりますが、同時に次のような問題も生みやすくなります。
- 画像所見だけで判断してしまう
- 症状との関連を十分に吟味しない
- 「写っている=原因」と短絡的に結論づけてしまう
たとえるなら、
「怪しそうな人物が映っていた」という理由だけで、
状況全体を検討せずに犯人と決めつけてしまうようなものです。
実際には、
- 画像に写っている異常と症状が一致しない
- 以前から存在していた変化が、今回の不調とは無関係
というケースも少なくありません。
画像では「写らない不調」がある
もう一つ重要なのは、
画像診断では評価できない領域が確実に存在するという点です。
例えば、
- 倦怠感
- 冷え
- 重だるさ
- 張り感
- 違和感や不快感
こうした症状は、本人にとっては明確な不調であっても、
画像上は「異常なし」と判断されやすいものです。
結果として、
- 検査では問題ない
- でもつらさは続く
- 治療の方向性が見えない
という状態に陥る方も少なくありません。
病院で改善しきれず、東洋医学を選択される方の中には、
このような経過をたどっているケースが意外と多く見られます。
「見つけてしまう」ことが負担になる場合もある
画像診断には、
「知らなくてもよかった情報を知ってしまう」
という側面もあります。
- 治療対象にならない軽微な所見
- 年齢相応の変化
- 直接の原因ではない構造的特徴
これらが見つかった場合、
- 「異常がある」という意識だけが残る
- 不安や恐怖が増幅される
- 体調への意識が過剰になる
といった心理的負担につながることがあります。
もちろん、
見つかって良かったケースが多いことも事実です。
ただし、「明らかにすること」が必ずしも安心や回復につながるとは限らない、という点は知っておく必要があります。
東洋医学が重視する「見えない情報」
東洋医学では、画像そのものよりも、
- 触れたときの反応
- 体の緊張やゆるみ
- 巡りの偏り
- 生活や体調の変化
といった、数値や画像に表れにくい情報を重視します。
これは画像診断を否定するものではありません。
むしろ、
- 画像で分かること
- 画像では分からないこと
を切り分けたうえで、
後者を補う視点として東洋医学が存在している、と考える方が現実的です。
画像診断+東洋医学という補完関係
画像診断は「構造」を知るための優れた手段です。
一方、東洋医学は「機能」や「流れ」、「変化の兆し」を捉えることを得意とします。
- 構造に問題がないかを確認する
- その上で、体の使われ方や回復力を整える
このように組み合わせることで、
「異常がないと言われたが、つらさは残る」
という状態に対しても、別のアプローチが可能になります。
次回予告
次回、第3回では
「保険診療」という制度に焦点を当て、
- 病名がつかないと治療が進みにくい理由
- 「未病」という東洋医学の考え方
について解説していきます。



